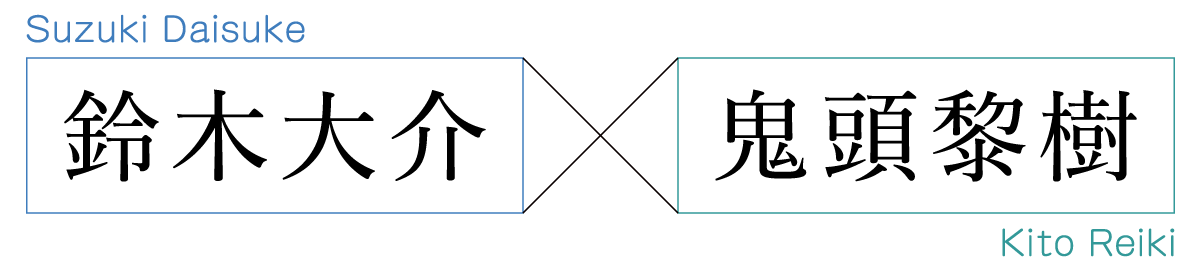|
第1回
GONTITIとの出会い |
|
|
鬼頭黎樹 初めてGONTITIさんを聴いたのは高校2年の時で1986年。GONTITIさんの初期の作品のプログラマーやプロデューサーをしていた、PSY・Sというバンドの松浦雅也さんが、ラジオ番組の「サウンドストリート」のDJをしていて、その年の6月に番組のマンスリーソングとしてGONTITIさんが参加した「本当の嘘」を発表したんです。それが最初に聴いた曲。ボサノバタッチで三上さんのボーカルがすごく繊細で、なんか気持ちいいと思いましたね。それでGONTITIさんの名前を憶えて、当時全盛だったレンタルショップに走って「冬の日本人」を借りました。大介さんは? |
|
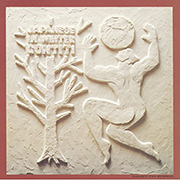
冬の日本人 |
鈴木大介 僕も同じ頃ですね。当時はFM情報誌がたくさんあったんですけど、そこでニューエイジミュージック特集みたいなのをやっていたんです。それを読んでGONTITIさんを知って、同じく「冬の日本人」を聴いたんです。 鬼頭 年齢が一つ違いだから。その時、大介さんは高校1年? 鈴木 そうですね。アコースティックなものに世の中の目が向いた時期で「ウィンダム・ヒル・レコード」というレーベルが流行ったりしていて、その流れでGONTITIさんにスポットが当たったんだと思います。でも実際に「冬の日本人」を聴いたら、違う路線だなって思ったし(笑)、むしろそっちが好きだったんですよね。ポップスやロックをずっと聴いていた方は、いわゆる耳心地いいアコースティックのインストゥルメンタルに“おっ!”ってなったかもしれないですけど、僕はずっとクラシックをやっているんで、そこはそんなに新鮮じゃない(笑)。でも「冬の日本人」の新鮮さにはびっくりしちゃったんです。エレクトロニクスとの共存というか……在り方がすごい。ナイロン弦のガットギターがメロディを弾くインストゥルメンタルって、あの頃は珍しかったんですよ。アールクルーとかくらい。 
鬼頭 鋭い。珍しかったかも。今でこそ日本人はボサノバ大好きですけど、我々が高校の時は……。 鈴木 ……なかった(笑)。あとはジョアン・ジルベルトぐらいかな。僕が“ギターを弾いてます”って言うと“歌はないの?”って聞かれてたくらい昔はギターと歌がセット。だからギターがメロディを弾くポップミュージックを探してたんです。 鬼頭 僕は(GONTITIの音楽の)色彩豊かなアレンジにひかれましたね。エレクトロニクスが斬新で鋭くて、ちょっと奇妙でユーモアもある感じ。 鈴木 初期の作品からぜんまいの音とかのサンプリングトーンをリズム楽器にしたり、ミュージックコンクレートっぽいところがありましたよね。それに“お~っ!”ってなった。 鬼頭 それが持ち味でしたよね。ご本人もおっしゃっていたと思うけど、すごく高価なシンセサイザーを借りられたかなんかで、それが“すごい!”ってなって取り入れて、アコースティックでもバリバリにギターが弾けるのに、そこに(サンプリングの音を)ぶち込んじゃってる。そしてナイロン弦を軸にしたポップミュージックは気持ちがよくて、日本人っぽくなかった。無国籍な感じ。箱庭……ジオラマみたいな音楽だなって思いましたよ。お二人は出身が大阪だけど、大阪って感じもしない。今はいろんな音楽が絶妙にブレンドされているからそうなっているってわかるけど、その時は“わからないけど、涼しい!”みたいな音楽(笑)……見たことのない島のようでしたね。 |
|
次ページ➡ 第2回 「we are here」 & マイベスト3 |